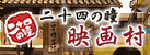「良人の貞操」は、山サンを囲んで準備からクランクインへと、
にぎやかに、そしてテキパキと進んでいった。にぎやかに、というところが、東宝の東宝たるゆえんで、
とにかく、あらゆるところでスタッフたちの意見がポンポン飛び出し、
ディスカッションの連続なのである。
しかも、その内容はすべて作品にかける情熱と
それぞれの経験や創造力から生まれるものだから、
どこまでも建設的だし、山サンの巧みな話術とユーモアが要所要所で
スタッフの血気をおだやかにさばき、的確に解決してゆくさまも、
また見事であった。尾羽打ち枯らし、意気消沈し、愚痴とやけくそ、
人の足の引っぱり合いに明け暮れる現在の映画界とは、
想像もつかない熱気と活気、
そして狂気とえいえるほどの「仕事への愛情」が、
そのころの映画界にはあったのである。俳優もスタッフも、だれかれの区別なくみんなが平等に一本のクギであった。
監督の命に従って、空にえがく楼閣は、一本一本のクギにささえられ、
作品として完成する。
フィルムの一コマ一コマに汗と思い出がにじんでいる。
私は東宝に移って、はじめて映画という仕事の、
一見チャランポランに見えて、底知れない深さ、楽しさ、苦しさを
スタッフの真剣な表情の中から教わった。
これは、高峰の著書『わたしの渡世日記』の一節である。
昭和12年、13歳で東宝(当時はその前身のP.C.L.)に引き抜かれ、
松竹から移籍した高峰秀子は、山本嘉次郎監督のもとで、
東宝移籍第一作「良人の貞操」に出演する。
先の一節は、その撮影現場で、13歳の高峰がじかに感じ取った思いである。
さらに、「渡世日記」では、続けて高峰はこのように綴っている。
一作品のスタッフは五十人から六十人。撮影日数は四十日から五十日。
中には一年以上の長期間にわたる作品もあった。四日で一本のドラマを作るテレビジョンなどと違って、根気と愛情、
そしてスタッフ全員のチームワークがとえれていなければ出来る仕事ではない。
画面に映らない「かげの人」たちは、画面に映る被写体、
つまり俳優たちのために髪を結い言い、ライトを照らし、カメラをまわし、
移動車のレールを敷き、クレーンをあやつる。「私はいったい、この大勢のスタッフの努力に対して、
俳優というクギとしての責任を果たしているだろうか?」
職業意識が、たとえ、わずかとはいえ、私の心に芽を出したのはこのころ
からである。誰に教えてもらったものでもない。本で読んだことでもない。五キロ、十キロのライトを
全身の力で押し上げるライトマンの光る汗を見ながら、
いつか私は、それを、経験から教えられていたのである。
人間は環境に慣れやすい動物だというけれど、
十三歳の私の柔軟な心に、人間はみな一本のクギという
東宝の「気風」が、ごく自然にしみこんでいったようである。
画面に出る人も出ない人も、みなが理想の楼閣を
作り上げたいという目標の前で、平等な「一本のクギ」である。
この精神を、高峰秀子は13歳にして、現場で感じ取り、
それを55歳で引退するまで持ち続け、
さらには、その精神を生み出してのち70年経った日、
「一本のクギを讃える会」として実現させたのである。
そして、働く者はその立場によらず地位によらず、
みなが平等なのだという思いは、終生、高峰の中に貫かれていた。
13歳で得た精神を、仕事をする上での矜持とし、
生きる上での信念として死ぬまで持ち続けた高峰秀子という人間に、
私は改めて尊敬の念を強くするものです。
一般財団法人一本のクギを讃える会
代表理事・松山明美